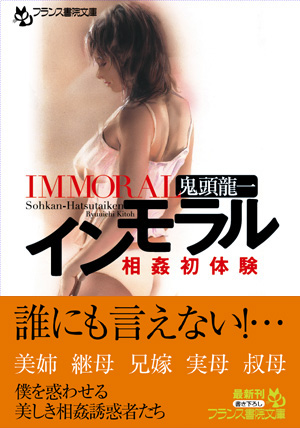-
検索
閉じる
- カート 0
- ログイン
- シチュエーション
熱化し牡香を放つ我が子の勃起が病室で震えている。
頬ずりし、舐め、体内に入れたい思いをこらえ、
奈津子は手で優しくしごきだす。
これが入院中の息子への、朝の日課だ。
痙攣する茎から飛散する精を浴びつつ母は決意する、
退院したら私の口と膣で受けとめてあげる、と。
- 登場人物
-
ゆみこ(34歳)実母
ゆうこ 姉
なつこ 実母
ようこ 姉
まゆみ 実母
本編の一部を立読み
奈津子はいぶかしげな表情を浮かべたまま、毛布をまくりあげてみた。
パジャマのズボンがまるでテントをはったように盛りあがっている。それを見ても、それが男の朝の生理であることに気づくまで、少し時間がかかった。無理もない。奈津子はもう十年以上も男と同衾していないのだ。
「た、立っちゃって……」
「小さくならないの?」
「なりっこないだろう」
「で、でも、どうしたらいいの?」
正直、奈津子にはどうすればいいのかわからなかった。
「お願いだよ、母さん。だ、出させて……出させてほしいんだ」
両手の使えない裕一には、切羽詰まった哀願だった。
「出すって? どうしたらいいの?」
「手で……手でこすってくれればいいんだ」
真っ赤になり、口ごもって言う裕一が可哀相だった。
奈津子はパジャマの上にそっと手をあてがい、痛むところをさするように、その手を動かしはじめた。
「駄目だよ、それじゃ。汚れちゃうよ、パンツのなかが。脱がせてよ」
裕一の言う通りだ。そう思ってパンツを押しさげたものの、いざ下腹で弓なりにしなったペニスを直に見れば、さすがに動揺せずにはいられない。
青筋を立てて反り返った陰茎、真っ赤に膨らんだ亀頭は、もう完全に一人前の大人のものである。しかし、まだ青白さを残した砲身は、いかにも硬そうで、若さをみなぎらせている感じだった。
「に、握って……しごいて……」
見つめたままためらう奈津子に、焦れた裕一が言った。
奈津子は、震えそうになる手でそっと、裕一のこわばりをつかんでみた。火傷しそうに熱い熱が、鋼鉄のように硬い感触が、てのひらにジーンと伝わってきた。
息子のペニスを、母親が……こんなことをしてもいいのだろうか……。
そんな疑念が胸にわだかまったものの、若く熱い血潮の実感には、何か感覚をうっとりさせずにはおかないものがあった。
裕一は頬を紅潮させたまま、うっとりと目を閉じている。
手に力を込こめて、ゆっくりとしごきはじめる。皮が剥けるたびに、赤く腫れ上がった尖端からツーンと男の性器臭が鼻をついっそう硬く、いっそう熱く、いっそう匂いが増してくるように感じられて、奈津子は手の動きをリズミカルに速めていく。
両手両脚をギプスで固定されて身動きできない体を、それでも裕一は必死に力ませて、こみあげてくる快感に酔っていた。
「母さん、もっともっと速く!」
奈津子のほうが焦ったように、腕全体を震わせ、力をこめて、裕一のペニスを小刻みにしごいた。