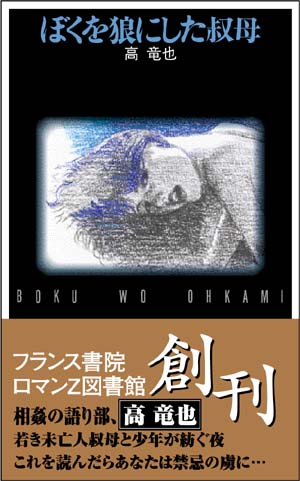-
検索
閉じる
- カート 0
- ログイン
ぼくに女を意識させたのは、白い肌と甘い美匂の叔母。ぼくに女体の神秘、女性のすべてを教えたのは叔母。ぼくに女を啼かせる性の奥技を伝授したのは叔母。元国際線スチュワーデスだった麗しき昌美叔母。今は未亡人でも、ぼくにとっては憧れの女性。誰よりも大好きで大切な、敬愛すべき女神。そんなぼくの前に現れては誘惑する少女。甘い媚肉と媚態で牡の本能を煽る熟女。そして今、ぼくは青き狼となった!
- 登場人物
-
まさみ(36歳)叔母・伯母
れいな 女子学生
まい(21歳)女子大生
はるか 女優・アイドル
つわこ 女子学生
本編の一部を立読み
「陽ちゃん、どうしてもしたいの?」
「したいっ、したいよっ……早くっ!」
「いけない子……いけない子……」
そう言いつつ昌美の手は、今にも噴出しそうな肉茎をつまんで、すっかり迎え入れる用意のできた秘孔に導いていた。
とてつもなく硬いものが、呆気なくズルッと陰唇を押しひろげて侵入した。昌美の指ではない、血の通った肉の帆柱が、女の道を一気に奥深くまで突き進んでいったのだ。
「動いちゃ駄目っ」
陽介の若々しい新鮮な肉棒が胎内でせわしなく動きまわる前に、昌美が制止の声をかけた。初めて女と接した陽介には酷な命令であったが、その言葉を忠実に守った。
交わる直前に、昌美の手によって一度放出されていたのが、このときに効を奏した。それがなかったなら、陽介はインサートした瞬間、ありあまるドロドロのスペルマを、火照った膣奥にぶちまけていただろう。
ともかく陽介はよく耐えて動かなかった。
柔らかくて温かい女の肉が、こわばりを優しく包み、時折り揉みしだくようにうねる。その甘美さは、とてもこの世のものとは思えなかった。陽介本人がじっとしていても、膣肉全体が微妙に蠢くのだ。
「あーっ、とても気持ちいい……よくってたまんないよ」
その言葉以外に、肉棒から生ずる快感をどう表現することができよう。
それは受け身になっている昌美にとっても同じだった。
久しく満たされなかった女の敏感な部分に、小ぶりではあるが、とてつもなく硬くて活きのよい甥の若い肉棒がはめこまれているのだ。ここまできてしまったからには、徹底的に快楽を貪るしかなかった。
だからこそ昌美は、陽介のせっかちになりがちな動きに、待ったをかけたのである。
まだ完全に大人になりきらない、中性的な陽介の尻肉をしっかりかかえこんだ。ひとつに繋がってしまったという現実感を味わっているうちに、昌美のなかで気分がどんどん高揚してくる。叔母と甥という背徳的な組み合わせが、むしろ正常な男女の交合以上に、性的感覚を煽りたてていった。
昌美は重たくのしかかる陽介の動きで、そろそろ限界が近いことを知った。
「あなたはじっとしていればいいの」
とかく男が積極的に動くと、射出が早くなる傾向がある。ましてや相手は、初めてセックスを経験している陽介だ。いくらお互いに動かないでいても、これだけ頑張れるのが奇蹟のようなものである。
昌美は陽介の腰からヒップの肉を優しく撫でながら、下から微妙に腰をまわした。膣口にきっちり食いこんだ肉棒を軸にしているから、膣襞が肉棒に擦られて、瞼が裏返ってしまいそうな快感が生じた。
「ああ……」
「叔母さん……なんだか変……ああ……漏れそうだよォ」
昌美のうっとりした声に合わせるように、陽介が五体をひくつかせながら情けない声を出し、体を突っ張らせた。
「いいのよ。お出しなさい……好きなときに出していいの」
このときすでに昌美は、これだけでは終わらないだろうと予測した。いや、陽介が求めなくても、自分から求めていくだろうと心に思っていた。