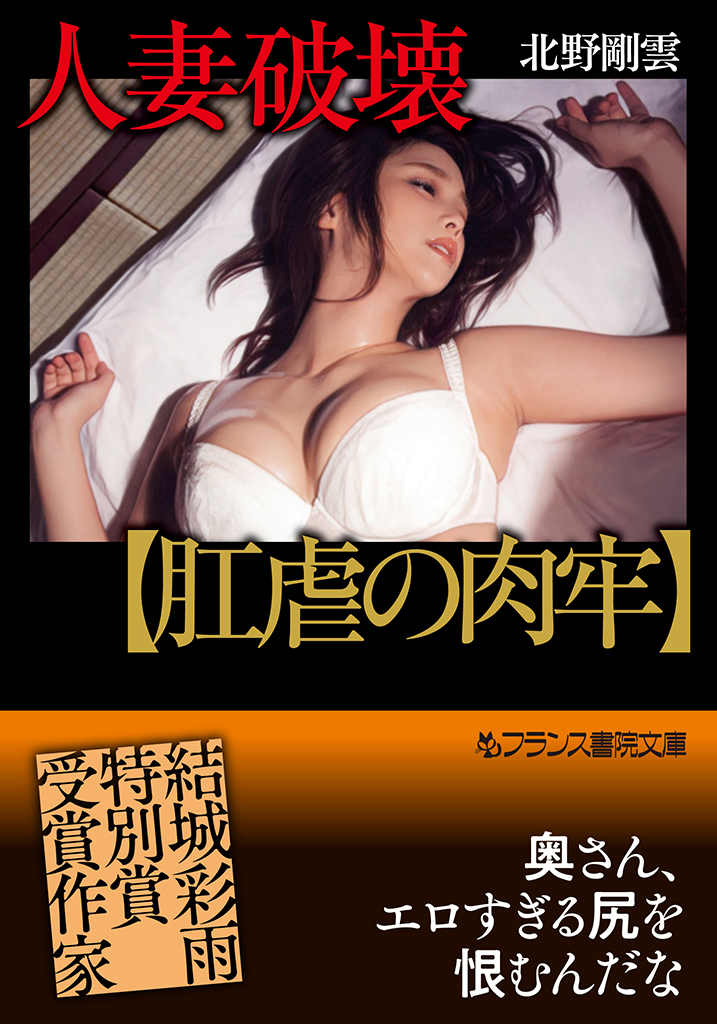-
検索
閉じる
- カート 0
- ログイン
弔いの媚肉 未亡人奴隷生活
本販売日:2024/04/23
電子版配信日:2024/05/02
本定価:1,111円(税込)
電子版定価:1,210円(税込)
ISBN:978-4-8296-4726-4
- ネットストアで購入
「だめッ、入れないで……アソコが裂けちゃうッ」
膣穴に巨根を抉り込まれ、美貌を歪ませて叫ぶ未亡人。
事故で夫を亡くした由紀子は、幼い娘との生活を守るため、
夫の上司に仕事の斡旋を依頼、面接会場へ赴くが……
鬼畜たちに裸に剥かれ、浣腸をされ、二穴を貫かれる。
奴隷契約書にサインさせられ、35歳は肉便器に……
- 目次
-
第一章 四十九日の法要を終えて
第二章 無惨に打ち砕かれた貞操
第三章 差し出されたマゾ奴隷契約書
第四章 肛姦で失神する由紀子
第五章 恥辱のマン習字に狂う理性
第六章 夫の遺影の前で埋まる他人棒
第七章 悪夢の浣腸バス
第八章 肉便器に堕ちた未亡人
第九章 地獄の花電車トレーニング
第十章 肛虐の大浴場
第十一章 絶望のアナルフック
本編の一部を立読み
第一章 四十九日の法要を終えて
(あなた、私たち、これからどうすればいいの……)
四十九日の法要を終えた篠宮由紀子は、仏壇に手を合わせて、遺影となった夫に心の中で語りかけた。
会社からの帰り道、横断歩道を渡っていた夫は、赤信号を無視して突っ込んできた黒い乗用車にはねられて死亡した。自宅アパートまであとわずか十分の距離だった。夫をはねた車はそのまま走り去り、いまだ犯人は捕まっていない。
父を早くに亡くし、頼れる親戚もなく、病気がちな母の代わりに生活を支えるため、高校卒業後すぐに地元の信用金庫に就職した由紀子は、いまどきの若者らしい青春を送ってこなかった。
夫と知り合ったのはその職場で、窓口業務に配属になった由紀子に一から仕事を教えたのが、三年先輩の夫だった。
そのとき夫はすでに両親を亡くし、天涯孤独の身で、同じような境遇の由紀子になにかと気を掛けてくれた。
もちろんそのときは二人とも男女の関係になるとは、少しも思っていなかった。
就職してから九年後、母が病死し、由紀子もまたひとりぼっちになった。
そんな由紀子を励まし、元気づけてくれたのが夫だった。
いつしか二人の間に恋愛感情が芽生え、由紀子が二十七歳の誕生日にプロポーズされ、夫は学生時代の奨学金の返済、由紀子は母の入院費などでお金がなかったため、結婚式を挙げずに入籍したのだった。
夫の薦めもあり、この機に由紀子は信用金庫をやめ、専業主婦になった。
それから六年、今年五歳になる娘の陽菜も産まれ、貧しいながらも幸せな家庭を築いていた。
それが夫の死で突然に奪われるとは……。
これから娘と二人、どうやって生きていけばいいのか。胸の奥に渦巻くどす黒い不安に、由紀子はいまにも押し潰されそうだ。
(だめよ、由紀子、陽菜のためにも強くならなければ)
法要で疲れたのか、膝の上で陽菜がすやすやと眠っている。まだ、この子が残っているのだ。天国の夫を安心させるためにも、しっかり生きていかなければ。
「このたびは残念でしたね、奥さん。篠宮くんを轢いた犯人は、まだ捕まっていないんでしょう」
法要を終えた夜、自宅アパートを夫が勤めていた信用金庫の支店長鮫島が訪ねてきた。相談があると由紀子が呼んだのだ。
「鮫島さん、ご足労いただきありがとうございます」
「なに、篠宮くんに線香をあげるついでですよ。気にしないでください」
鮫島が夫の仏壇に手を合わせる。
「まったく、これからの金庫を背負って立つ担い手だったのに、こんなことになるとは、本当に残念です」
「主人もそう言っていただければ、悦びますわ」
「それで、奥さん、相談というのは」
狭いアパートのリビングで、ちゃぶ台越しに向かい合って座ると、さっそく鮫島が呼ばれた理由を聞いた。
四十代前半の鮫島は、筋骨隆々の大柄な男で、髪の毛をオールバックにし、その顔つきは名前の通り凶暴な鮫を思わせた。若くして支店長になった切れ者だが、出世のためならなんでもすると、悪い噂も絶えない人物だ。
もっとも、その仕事ぶりは確かで、一緒に働いていた夫も絶対の信頼をよせていた。また、鮫島もなにかと夫に目を掛けてくれ、よくこの狭いアパートにも娘へのお土産を片手に遊びに来てくれた。
『鮫島さんはいい人だよ。人の噂はあてにならないな』
生前、夫がそう言っていたのを憶えている。
だが、由紀子は夫ほどこの男に気をゆるすことができなかった。
信金に勤めていたときもそうだが、結婚してからも夫の目を盗んでは由紀子を口説こうとするのだ。一度など背後から近づき、お尻をいやらしくなで回したので、頬に平手打ちを喰らわしたこともある。
それ以後は由紀子に触れることはなくなったが、それでもゾッと背筋に寒気が走って振り返ると、ニヤニヤといやらしい目つきでこちらを見つめていた。
夫がいないいま、そんな男を家に入れるのはためらわれたが、これからの生活を考えると背に腹は代えられない。できるだけ女を感じさせないように、肌を隠す喪服姿で彼を迎えた。
「じつは、職場に復帰できないかと思いまして、それで、支店長の鮫島さんにお口添えいただけないかと……」
娘を育てるためにも、すぐに就職したいが、特段の資格を持っていない由紀子は、元の職場に再就職できればありがたいと考えたのだ。
「そうですね。篠宮くんにはよく助けてもらいましたし、こんな事情ですから、上に相談してみましょう」
なにか条件をつけられるかと思っていたが、拍子抜けするほど鮫島がすんなりとうなずいた。
「ご迷惑ではありませんか」
「なに、六年前まで働いていたんですから、即戦力になりますし、問題ありませんよ、奥さん。それより他に困っていることはありませんか。私にできることなら、何でも言ってください」
「ありがとうございます。お口添えいただけるだけで充分ですわ」
鮫島は由紀子が考えていたような危ない人物ではないのかも知れない。夫が言っていた通りだ。警戒していた自分がバカみたいだと由紀子は思った。
「復帰の件、これから上に掛け合ってきます。明日にはいい返事ができると思いますよ」
しばらく世間話をした後、鮫島がそう言って立ちあがった。
「よろしくお願いします」
玄関まで見送りに出ると、由紀子は深々と頭をさげた。