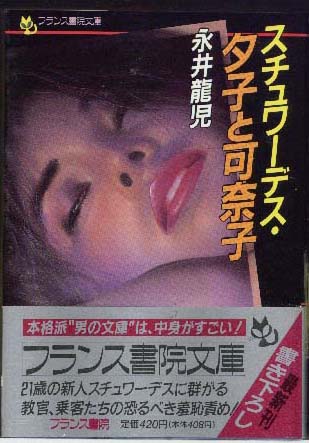-
検索
閉じる
- カート 0
- ログイン
- シチュエーション
指が這う――しっとりとした太腿を。
指が抉る――潤みきった粘膜の襞を。
「いや! さわらないで……」
抗いの言葉とは裏腹に、女盛りの曲線が波打つ。
盲目の夫の見えない視線を意識しながら、女陰を犯す指の蠢きに、
ざらついた舌の感触に、熟れた女体は喘ぎを吐きだし、
背徳の絶頂を告げる……
- 登場人物
-
たまこ 人妻
さよこ 女子学生
かずよ(40歳)人妻
本編の一部を立読み
「どうしてもなさるんですか」
「ああ、するさ。自分だってしたいくせに、この嘘つきめ!」
「いやです。嘘じゃありません」
「よし、それなら、よがり声を出すなよ。出したら承知せんぞ」
金栗は仰向けになっていた多満子を乱暴に裏返した。後ろ手縛りにされている両腕が上へきて、多満子はつんのめった。
「膝を立てろ」
と金栗が多満子の太腿を叩いた。多満子はもがきながらのろくさと言われたとおりの恰好になった。両手をつければ四つん這いの形だが、そうではないから、顔と肩を布団について上体を支えた。前のめりの姿勢である。
四つ足の動物が、前足を折って後ろ足だけで立ち上がろうとしているのと同じだから、多満子の大きなヒップはいやがうえにも突き出されている。
「先生、ひどい――」
こんな恰好はしたくないと、膝を伸ばそうとしたとき、金栗が多満子の腰を引きつけ、屹立した漲りを女の一点に刺し通した。
「あっ、ああっ――」
思わず火を吐くような声をあげた多満子は額を布団にこすりつける。
彼女の奥深く一気に侵入してきた金栗のそれは、鋭い感じがして、一瞬、総毛立つような寒気がしたほどである。夫の信次の感触はもう忘れかけているが、金栗のように鋭かったという記憶はない。
鋭い感じがかならずしもいいというわけではなかったが、強烈であったことはたしかだった。多満子は前のめりになった背筋をさらにのけぞらし、激しく首をうち振って苦しげに喘いだ。
「これでもまだいやだと言うつもりか」
という金栗の声が、どこか遠くから聞こえてくるようである。それでいて、男の荒い息づかいは、はっきりと間近に聞こえている。それは多満子の官能の火を煽り、燃え広がらせていく。
金栗の動きもまた荒々しかった。これでもか、これでもかといわんばかりに、絶え間なく突き立てる。それが鋭くて強烈なのである。多満子はこらえようがなかった。それでなくても、三年ぶりのまじわりは新鮮で、昇りつめる速度は早い。速度はしだいに加速度がついてくる。
「どうだ、いやか。いやか、よ――」
と煽る金栗の挑発に、
「いやよ、いやよ、いやいや、いや――」
多満子はうわごとを口走るように調子を合わせていた。もし金栗が「どうだ、いいか、いいか」と煽れば、「いい、いい」と彼女は口走っていたにちがいない。多満子は自分が何を言っているのか、わかっていなかったのである。
「ざまみろ、よがり声をあげやがって。よく覚えておけよ。もう二度と、いやだのやめてくれなどとは、言うわせんからな」
金栗は息づかいも激しく、多満子の尻をぴしゃぴしゃと叩いて喚いた。