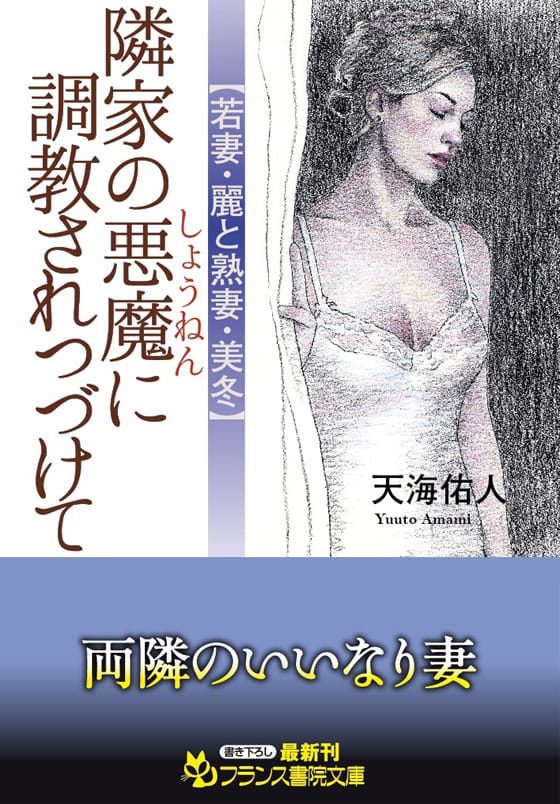フランス書院文庫 ヒストリア since 1985

- 1980年代 それは相姦小説と本格凌辱から始まった
-
フランス書院文庫が創刊されたのが1985年。当初は相姦系と凌辱系という二つのジャンルがあった。
相姦小説とは、母と息子、姉と弟、叔母と甥……などが禁忌を乗り越えて関係を結ぶ作品である。「乗り越えて」と書いたが、80年代は母を押し倒したり、姉と無理やり関係を結ぶといった男の一方的な気持ちが先行し、それに女性がズルズルと溺れていく展開が多かった。
代表的な作品は『叔母・二十五歳』(鬼頭龍一)、『実母と義母』(高竜也)、『義母と姉の寝室』(由布木皓人)……など。当時の相姦小説はかなり暗く重い雰囲気に彩られていたのが特徴である。
もう一つの潮流が凌辱系だった。男が力ずくで女をモノにする作品は、後に「本格凌辱」と呼ばれるようになる。
濡れ場に入る前の序盤がしっかり描かれ、緻密に張り巡らされた罠にヒロインは堕ちていく。代表的な作品は『女教師・二十三歳』(綺羅光)、『肉牢』(蘭光生)、『人妻 悪魔の園』(結城彩雨)などが代表作である
ヤクザ(今でいう半グレなども含む)が凌辱者であることも多かった。圧倒的な権力や暴力を武器に、気高く美しい女性を狩っていく。まさに力こそすべて――日本が高度成長していく時代、読者の男性も、登場する凌辱者たちも自信に満ち溢れていた。
暗く重い相姦小説は今ではもう見かけなくなったが、「本格凌辱」は35年以上にわたって続き、現在はフランス書院文庫Xというレーベルで名作が復刊されている。ご興味がある方はぜひ手にとってみてほしい。
- 1990年代 フェチとマゾヒズムの台頭
-
相姦小説は、この頃から「誘惑小説」へと変化を始める。女性が積極的に男性をリードし、男は基本的に「待ち」の姿勢で、義母、兄嫁、女教師など、年上の女性から手ほどきを受けるという形態が隆盛を極める。
それでも当初は80年代の「禁忌」の雰囲気を引きずっていた。
義母が息子と寝る場合、禁断の一線を踏み越えてもいいのか、ヒロインは悩み苦しむ。当然すぐには体を許さない。そのために発明されたのが、「サブヒロインシステム」だ。本命のヒロインと寝る前に、叔母や隣家のお姉さんや女家庭教師といった「サブヒロイン」が少年の相手役を務め、初体験も本命以外の女性で済ませる。やがて二人の関係を目撃したメインヒロインが(他の女に奪われるくらいなら私が……)とようやく重い腰をあげる。最終章で本命と結ばれるというパターンも多かった。
80年代より濡れ場は明らかにハードになった(それ以前は社会倫理上、書きたくても書けなかった)。『義母 特別授業』(牧村僚)、『若義母ダブル交姦』(西門京)を読めば、濡れ場の進化がうかがえるだろう。
『性獣家庭教師・狂わされた母と息子』(田沼淳一)のように、誘惑と凌辱を意図的にミックスさせたドロドロした作風も現れた。いずれにせよ、求められたのは濃厚な濡れ場である。90年代半ばから、『隣りのお姉さん・少年狩り』(櫻木充)などの、脚フェチ、ストッキングフェチの嗜好を満たす作品が出現しはじめた。映像はともかく、フェチは活字では表現しにくいと思われていたが、実力のある作家たちの登場が状況を変えた。
凌辱系では自ら被虐に落ちていくマゾ女性を扱う作品が一大ジャンルを築いた。『女教師二十四歳 闇に蠢く白い媚肉』(佳奈淳)、『女教師・Mの教壇』(伊達龍彦)などである。
凌辱され、堕ちていくのではなく、自らの意志で堕ちることを望む女――マゾ気質な女性が読者の人気を集めた。このジャンルからは、可愛らしいヒロインが続々と生み出された。ちなみにライトノベルのメイド系ヒロインには、マゾ小説のヒロインと似た匂いを感じる。「ご主人様、ご奉仕いたします!」と主人にけなげに服従を誓うヒロインは、マゾ小説のヒロインそのものである。
また、凌辱系でユーモアを含んだタイトル、作品が目立ちはじめた。『セーラー服凌辱ゼミナール』などを執筆した海堂剛などが代表的な作家である。凌辱なんてマジにやってどうすんの? とでも言わんばかりの軽く、ゆるい作風が受け入れられるようになったのは、世相を反映していると言ってもいいだろう。
- 2000年代 全肯定誘惑と暴走系
-
この頃からヒロインの数が増え、「ハーレム」という世界観が生まれ始める。それまでは本命の義母、当て馬の叔母というダブルヒロイン制だったのが進化し、三人目のヒロインとして家庭教師のお姉さんなどが登場するようになった。
『三人の家庭教師 叔母とママと先生と』(鏡龍樹)、『年上三姉妹【素敵な隣人たち】』(弓月誠)、『叔母と三人の熟夫人 いたずらな午後』(楠木悠)など、ヒロインが三人であることを明示するタイトルも増えてきた。
物語のエンディングにも変化が現れた。90年代までは本命のA子、当て馬のB子から誘惑された末、最終的には主人公はA子を選んでいたわけだが、ハーレムモノでは、A子、B子、C子と関係を結んだあげく、そのままみんなと仲良く暮らしました(もちろん女性は同意の上)――という結末になることが増えた。
さらに『二つの初体験 熟義母と若叔母』でデビューした神瀬知巳の登場とともに誘惑小説はより甘く、優しくなった。キーワードは「全肯定」である。
以前であれば、息子が家に引きこもっていた場合、義母はなんとか息子を外の世界に連れ出そうと努力し、その手段として自らの肉体を提供したり、外の世界に出ることを決意した息子への「ご褒美」としてセックスを許した。
だが、全肯定スタイルでは、ヒロインは「引きこもっていいの。今のままの××ちゃんがママは大好き。(なんなら)ずっとママが養ってあげる」と提案し、さらに最高のセックスまで体験させてあげる。
引きこもっていても息子が大好き。いや、むしろ引きこもっているあなたが大好きという新たな価値観を提示した。この年上熟女による母性あふれる「全肯定」が、仕事や家庭で疲れた中高年男性にどれだけ癒しを与えただろう。
結果的に、ヒロインである熟女は経済的に自立している女性が多かった。要はバリバリ働いている「稼げる女」である。ポルノには男性の願望が他のジャンルよりも先鋭的に表れる傾向にあるが、高収入の女性(美人で優しくてセックスも最高)に養ってもらいたいという男性の夢がそこには描かれていた。
なんでも望みを叶えてくれる「隣人」としての母親を描いた『危険な同居人 ママと美姉・プライベートレッスン』(秋月耕太)、『最高の楽園 四人のお姉さまと寝室』(上原稜)といった作品も登場し、この時代は「どれだけ甘いか」を競い合うように、誘惑小説は進化を遂げていった。
一方で、凌辱小説では「暴走系」が新たなムーブメントを起こす。悪魔のような少年が年上の女性を徹底的に凌辱し尽くす。暴走し始めたら手がつけられないことから、エヴァン〇リオンの主人公になぞらえ、編集部内で〝暴走系〟と呼ばれるようになった。
代表的な作品は『女教師姉妹』(藤崎玲)、『年上の美囚 継母と若叔母』(麻実克人)、『若妻と誘拐犯 密室の43日間』(夏月燐)などである。
とにかく濡れ場への持ち込み方が、暴力的なまでに早い。開始から数ページで、悪魔少年は「ママを僕の専用奴隷にしてやるよ」と宣言。手段を選ばず、力ずくでモノにする。
物語の流れは、本格凌辱を「起承転結」だとすれば、暴走系は「起濡濡濡」とでも言おうか。がっつりとした濃厚な濡れ場が見たい、という読者の欲求に応える作風だった。暴走系が勢いを増す一方で、複数の凌辱者が一人の女性を凌辱(輪姦)するような作品は廃れていった。男性たちが女性を「シェア(共有)」する作品は減り、一人の凌辱者が複数の女性を独占するハーレム展開が好まれようになる。ここにきて、誘惑小説と凌辱小説の結末がほとんど同じ(ハーレム)になるという奇妙な現象が生まれる。
- 2010年代 新しい風を求めて
-
2010年代の誘惑小説は『僕とメイド母娘 ご奉仕します』(青橋由高)から始まった。弟レーベルである「美少女文庫」の人気作家が、メイドという新しい属性を武器に、中高年向けの官能小説に新風を巻き起こした。
2010年代は基本的に2000年代に生まれた流れを引き継ぎつつも、さらに新たな要素を付け加えた、「コラボの時代」と言えるかもしれない。この流れに乗り、凌辱小説で一気に頭角を現したのが御堂乱だ。「催眠」「時代小説」「特撮ヒロイン」など、ありとあらゆるジャンルをどん欲に取り入れ官能小説として成立させる手腕は、新しいものに飢えていた読者に熱狂的に迎えられた。『四匹の女教師【言いなり】』の冒頭は、屈指の名文として現在も語り継がれている。
『四人の熟未亡人と僕【旅行中】』(小鳥遊葵)のように、ヒロインの数が3人から4人へと増え、さらに旅行中の出来事を描くなど、自宅以外の場所で濡れ場を描く作品も増えた。
また、『女子高剣道部』(甲斐冬馬)、『義母風呂』(天崎僚介)のように、限定されたシチュエーションでの作品が目立ち始める。癒しを与えられる場という意味で、温泉モノが増えたのもこの時代の特徴だ。凌辱系では暴走系の表現手段、特に女性視点の表現が進化していった。『【若妻・麗と熟妻・美冬】隣家の悪魔に調教されつづけて』(天海佑人)では、悪魔少年に調教されるヒロイン側の視点から物語が描かれている。
従来の凌辱小説は男視点がメインで、憧れの女性への妄執をどれだけ描けるかが重要なポイントだった。ところがこの時代は、どれだけ女性の気持ちを心の声で語らせつつ、物語を展開させるかが鍵になっていた。男性視点のみで物語をつむぐことは、強引で、ひとりよがりになってしまう。そこを筆者の技量で、いわば力わざで進めていくというところに、凌辱小説のひとつの面白さがあった。だがこのやり方では、読者に説得力をあたえられない時代になってしまったということなのかもしれない。
また『母娘の檻 陽子、あゆみ、舞…全員が牝になった』(藤崎玲 原作・四畳半書房)のように、漫画のノベライズなど、他ジャンルとのコラボレーションが進み、若い読者を官能小説に呼び込むきっかけになった。
新人作家がつぎつぎとデビューをしたのも特筆すべき点だ。
「フランス書院文庫官能大賞」が年二回の〆切になったのを皮切りに、ぞくぞくと新しい才能がフランス書院文庫に登場し、ベテラン、中堅作家を押さえて月間一位となる月も珍しくなかった。
2010年代の掉尾を飾るように、フランス書院文庫官能大賞でひさしぶりに「大賞」が登場。『人妻拷問【絶望受胎】』(妻木優雨)。
この時代、「物言わぬ読者」の声は、新しい企画を、そして新しい才能を、常に求めつづけているかのようだった。 - 2020年代 官能小説はどこへいくのか?
-
そして現在、フランス書院文庫は創刊から35周年目を迎える。次はどのような新しい潮流が生まれるのだろうか?
ネットではすでに人気を博している〝寝取られ〟かもしれない。あるいは〝時代官能〟かもしれない。戦隊ヒロインなどの新しいヒロイン属性かもしれない。
個人的には、全肯定の誘惑系ハーレムと暴走系という二つの大きな流れを軸に、よりジャンルの細分化が進んでいく気がしている。
この35年間、何かのトレンドを編集部が作り出してきたわけではない。著者たちの旺盛なイマジネーション、そして読者の熱烈な支持によって自然発生的にジャンルが生まれてきた。この場を借りて、御礼を申し上げたい。
これからも我々は、著者と読者に寄り添い、新しい官能の歴史を創り出していきたい。
フランス書院編集部